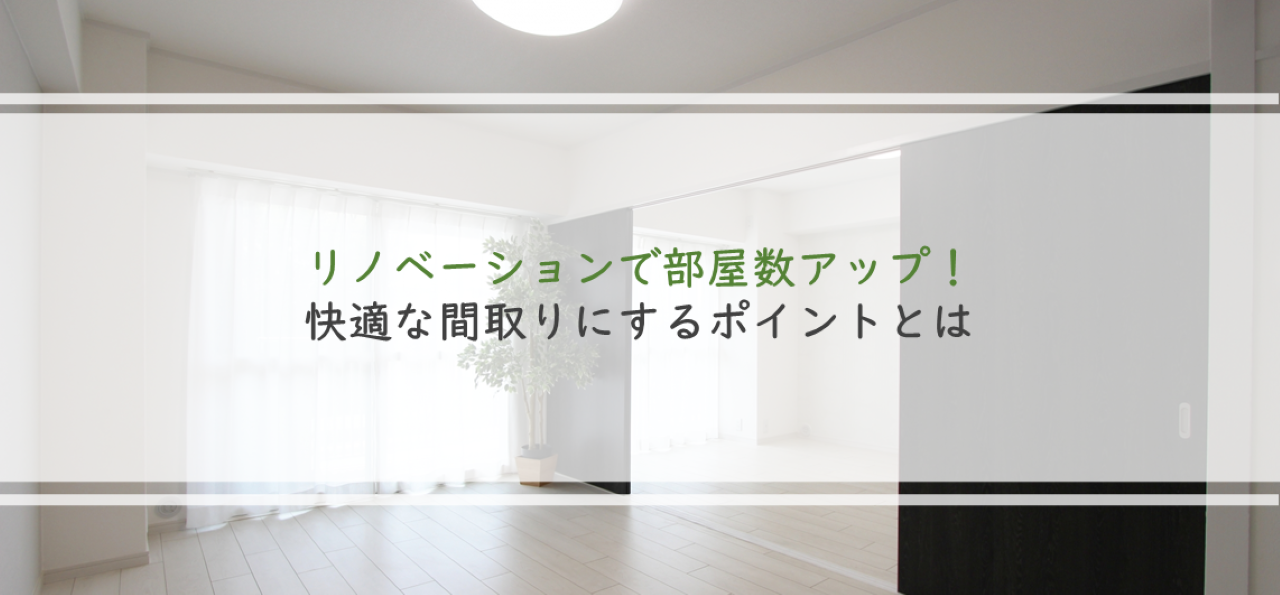
リノベーションで部屋数アップ!快適な間取りにするポイントとは
限られた住空間でも「可変性」「機能性」「デザイン性」を両立するためには、間仕切りの工夫やロフト・中二階の活用、そしてプロによる最適な設計が欠かせません。
この記事では、可動式パーティションや折りたたみ式パネルを使った柔軟な間取りづくりから、ロフトベッドや中二階の設置による上下空間の有効利用、さらには壁面収納や多機能家具で実質的な居住スペースを広げるコツまで順に紹介します。
「部屋数を増やしたい」「収納を確保してスッキリ暮らしたい」「将来のライフスタイル変化にも対応できる間取りにしたい」——そんなお悩みを持つ方に向けて、実践的なリノベーションアイデアを詳しく解説していきます。
間仕切り(パーティション)の活用で可変性のある空間を

間仕切りを活用して可変性のある空間を実現する方法を、以下で詳しく紹介します。
固定壁ではなく可動式パーティションを採用
まず、固定壁ではなく可動式パーティションを採用しましょう。天井吊り金具やレールを使ったスライド式の間仕切りパネルは、使わないときに壁際へ簡単に収納でき、部屋を広く使えます。
デザインや色も豊富で、DIYで取り付け可能なものも多く、初期コストを抑えながらインテリア性もアップ。例えば、リビングと書斎を可動式で仕切れば、来客時には「広いリビング」として使い、普段は書斎スペースを確保できます。
折りたたみ式パネル(フローリング上設置タイプ)
折りたたみ式パネルは、必要なときだけ開閉でき、床にレールを設置するタイプより施工費用を抑えられます。コンパクトに畳めるため、掃除や模様替えの邪魔になりません。
ただし、音漏れが多少気になる場合は、吸音マットや布製カーテンと組み合わせると効果的。目隠し効果は控えめなので、完全なプライベート空間が必要な場合は他アイテムとの併用がおすすめです。
また、ルーバータイプのパネルを使えば、角度調整できる羽根が通気性と採光を両立してくれます。部屋を完全に閉じず「半個室」にすることで、子どもの遊び場やワークスペースとして快適に活用できます。風通しを確保しつつ目隠しもできるため、換気を重視したい在宅ワークスペースにも最適です。
半透明素材やガラススクリーンで光を取り込む
半透明ガラスや強化ガラスのパーティションなら、採光を確保しつつ視線をほどよく遮ります。独立性を保ちながらも昼間は光が回るため、室内が暗くなりにくいのがメリットです。
また、ルーバータイプを選べば羽根の角度調整で通気性と採光を両立可能。完全に閉ざさず「半個室」にできるので、子どもの遊び場やワークスペースにもおすすめです。
ロフトや中二階の設置で空間の上下利用を図る

ロフトや中二階の設置で上下方向の空間を有効活用する方法を、以下で紹介します。
ロフトベッド・ロフト床の設置
ロフトベッドを設置し、下部をワークデスクや書棚に活用することで、「ベッドルーム+書斎スペース」の一体化ができます。子ども部屋やワンルームでは、下段に勉強スペース、上段を就寝スペースとする二層構造も実現できます。
また、ロフト下をクローゼットや引き出し式収納に充てれば、限られた床面積を圧迫せずに収納量を拡張できます。中段に可動式の板を設置すれば半ロフト棚として使え、空間を「下:通常床」「中央:棚」「上:ロフト床」の三層に分割するのもおすすめです。
中二階(メザニン)の導入
天井高が2.7m以上ある場合は、中二階(メザニン)の導入を検討しましょう。1階をリビング+ダイニング、途中の中二階を書斎カウンターや趣味部屋、2階を寝室といった役割分担ができます。
梁や構造躯体の耐荷重を確保すれば、デザイン性の高い遊び心ある空間づくりも可能です。階段やはしごは、折りたたみはしごや交互踏みのスモール階段を選ぶと、床面積を有効に使えます。
中二階の床面積は小さくても、子どもの遊び場や書類保管スペースとして“プラスαの個室感”を生み出せます。
収納の最適化で実質的な居住面積アップを実現

部屋数を増やしたい背景には「手狭感を解消したい」「物があふれているから個室を作りにくい」といった理由も少なくありません。
まずはどこに何をしまうかを見直し、空間をスッキリさせることで、部屋を分割しやすい状態を作りましょう。
壁面収納・吊り収納の活用
床から天井まで造作した壁面収納を設けることで、生活用品や書籍を縦方向にたっぷり収納でき、床スペースに物が散らばりにくくなります。扉付きタイプにすれば、中身を隠してホコリを防ぎつつ、間仕切りを設置した際の視覚的な圧迫感を減らせるでしょう。
さらに、キッチンや洗面、トイレなどの水まわりにも吊り戸棚を取り付けて上部空間を使い切れば、廊下やリビングの床面積をより広く確保可能です。
収納家具を置く場所を減らすことで、パーティション導入時に生じる床面の分断が起こりにくく、すっきりした空間を維持できます。
多機能家具の導入
引き出しや跳ね上げ式の収納付きベッドを使えば、クローゼットなしでも衣類や布団、カバンなどをすっきり収納でき、空間を有効活用できます。
特に間仕切りで部屋を分ける場合、家具の置き場所に困りやすいため、ベッド下収納は動線の確保にも有効です。収納内部を仕切って整理すれば使い勝手も向上し、折りたたみ式デスクを併用すれば作業スペースも確保可能です。
収納力と使いやすさのバランスを考え、ベッドの高さは90〜110cmが目安です。
デッドスペースの活用
廊下や階段下のデッドスペースに可動式の引き出しやオープン棚を設置すると、リビング側の床面積を使わずに収納が可能です。間仕切りで細かくエリアを分ける際も、廊下に荷物置き場があれば室内に物を置かずに済むため、間取り変更をスムーズに進められます。
また、ドアの裏や家具の裏などのわずかなすき間には、ハンガーラックや可動式フックを取り付けて帽子や傘、掃除道具を掛けておくと、収納家具を設置するスペースを節約できます。
これらの工夫により、デッドスペースを有効活用しながら部屋をすっきりと保つことができ、限られた面積でも快適な暮らしを実現できるでしょう。
可動式間取りアイデアで将来のライフスタイル変化にも対応

部屋数を増やすリノベーションは、子どもが成長して巣立ったあとや、テレワークの終了後には不要になることもあります。
空間を一度つくったら固定されるのではなく、「後々のリフォーム費用を抑えたい」「ライフステージに応じて間取りを戻したい」という要望に応えられる設計が重要です。
梁や柱の位置を活かした間取り
撤去できない柱や梁は制約ではなく、デザイン要素として活かすことで機能的で美しい空間を作れます。
柱を間仕切りに組み込み、梁下に可動パーティションを設置すれば、立体感と開放感を両立可能です。将来は簡単にワンルームに戻せます。
引き戸・折れ戸で“壁ごと”可動
引き戸(スライドドア)をリビングと寝室の間に設置すれば、来客時は閉めてプライバシーを確保し、将来的には一体空間としても活用可能です。二重の引き戸は遮音性・断熱性にも優れ、生活スタイルの変化に柔軟に対応できます。
また、折れ戸とアーチ型の垂れ壁を組み合わせれば、開放感と通風を確保しつつ、部屋をゆるやかに区切ることができ、空間全体に優雅な印象を与える間取りが実現します。
リノベーションのメリット

リノベーションのメリットを、以下で詳しく紹介します。
※「リノベーション」と「リフォーム」の違いについては、こちらの記事で詳しく見られます:
リノベーションとリフォームの違いとは?あなたに合う選択はどっち?
専門家の視点で最適な空間設計が可能
リノベーションには、専門家の視点で最適な空間設計が行えるという大きなメリットがあります。
建築士やインテリアデザイナーなどプロが、ライフスタイルや家族構成、将来的な使い勝手を考慮しながらプランを立てるため、DIYでは実現が難しい動線設計や収納計画を最適化できます。
例えば、キッチンとダイニングの位置関係を見直して家事動線を短縮したり、収納スペースを無駄なく確保したりすることで、日々の暮らしが格段に快適になります。
断熱性・防音性・配線など、DIYでは難しい部分も改善
リノベーションでは断熱性や防音性、配線・配管などの性能面も専門的に改善できます。古い建物の場合、断熱材やサッシを新しいものに交換しなければ冬場の寒さや夏場の暑さに対応しづらいことがあります。
しかし、断熱改修を行うことで室内の温度変化を抑え、省エネルギー性能を向上させることが可能です。
さらに、隣家や上下階の音が気になる場合は防音工事を施し、壁や床に遮音材を入れることで騒音を軽減。配線・配管の経年劣化にも対応でき、増改築のタイミングで電気配線や給排水管に更新すれば、安全性を高めるうえに省メンテナンス化にもつながります。
長期的な資産価値の向上が期待できる
リノベーションによって性能や間取りを改善すれば、築年数の古い物件でも資産価値を高めることが可能です。
「新築に近い状態」に再生することで、不動産市場での評価も上昇します。特に投資用物件では、省エネ性能や人気の間取りを備えたリノベ物件は入居率が上がり、家賃の維持にもつながるため、収益性向上にも貢献します。
プロに頼むべきポイントと注意点

リノベーションや大規模改修を検討する際、どこまでを自分で行い、どこから専門家に依頼するかの見極めは非常に重要です。
特に以下の3点は、専門的な知識と経験を持つプロに任せることを強くおすすめします。それぞれの理由と注意点をまとめます。
建築基準法・構造耐力への配慮
間取り変更や壁の撤去・追加に際して、まず確認すべきは構造耐力です。
自己判断で柱や梁を移動・撤去すると、建物全体の強度低下を招き、倒壊リスクや不具合につながる恐れがあります。
また、耐震基準や用途変更の手続きなどは建築基準法に則って進める必要があるため、建築士や構造設計士へ現状調査と設計プランの検証を依頼しましょう。
例えば、1階の壁を抜いてオープンなLDKにしたい場合でも、どの壁が耐力壁(構造を支える壁)なのか、床・天井の補強方法、基礎の強度確認など、DIYでは判断が難しい要素が数多くあります。プロは耐力計算や国の基準に基づく改修プランを作成でき、安心して工事を任せられます。
配線・配管の取り回し
電気配線や給排水配管は、見えない部分ながら安全性と快適性を大きく左右します。
キッチンや水まわりの位置変更では、ガス・給水・排水・電気の経路再設計が必要です。誤った施工は漏水・漏電・火災リスクにつながります。
また、築年数が経過した住宅では配線・配管の老朽化が進んでいる場合も。設備業者・電気工事士であれば、法令に沿った安全な取り回し計画や、必要に応じた配管スペースの確保まで設計可能です。
さらに、床下や天井裏のスペースを有効活用して配線・配管をまとめれば、点検・メンテナンス性が高まり、将来のトラブル低減にもつながります。
コストバランスの最適化
予算調整は、プロの知見により無駄を省き費用対効果を最大化できます。
同等性能の仕上げ材・設備でも、メーカーや意匠で価格差が生じます。プロは複数商材・工程を比較し、コストを抑えつつ必要品質を満たす選択肢を提示できます。
見積もりでは、人件費・廃材処理費・申請費などの内訳の可視化が重要です。どこにどれだけ費用がかかるかを把握し、投資すべき箇所と抑える箇所を明確にすることで、予算超過を防ぎつつ満足度の高い計画にできます。
(例:断熱窓は「断熱性能グレード」が同等でも、枠材・ガラス仕様・意匠で総額が大きく変動)
まとめ

可動式間仕切りを活用すれば、用途に応じて空間を仕切ったり広げたりでき、半透明パネルやルーバーで採光と通気も確保できます。
ロフトや中二階は上下のデッドスペースを活用し、ベッド下・階段下の収納を整えることで、床面積を圧迫せずに収納力を高められます。
さらに、壁面収納・吊り戸棚・多機能家具を導入すれば、置き家具を減らして動線をスムーズにし、パーティション設置時の圧迫感や使い勝手の課題も軽減できます。将来ワンルームに戻す想定なら、引き戸(スライドドア)や折れ戸を外すだけで大空間へ復元できる柔軟性も魅力です。
最終的には、プロの視点で断熱改修・遮音対策・配線・配管計画など性能面を確保し、資産価値の向上まで見据えたリノベーションが、ワンランク上の快適な住まいへの近道です。
これらのアイデアを組み合わせ、家族構成やライフステージの変化にも対応できる可変性の高い理想の住空間を手に入れましょう。
リバータスでは、リノベーションに関わる多岐にわたる工程を一括で請け負い、低コストで高品質なサービスを提供します。お客様のニーズやこだわりに応じて、物件の新たな価値を創出し、住まいをより快適で安心できる空間へと生まれ変わらせます。
理想の住まいを実現するため、ぜひお気軽にご相談ください。
